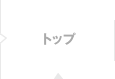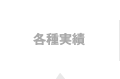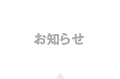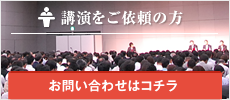コラム
税理士にとってはの経営者保証のガイドライン!どう捉えますか?
少しずつですが、「経営者保証に関するガイドライン」の認知度に
中小企業同友会の調査によりますと、保証をはずせたのは4%程度
同友会の会員企業で約30%なのですから、全国的には、もっとこ
経営者への意識づけ・・・という意味においては、やはり、顧問税
ただ、ここで一つの問題が発生します。
もし、顧問先から「それでは、先生、連帯保証を外したいのでお手
この際、顧問税理士の対応としては、以下の3通りがあると想像い
1.「できません」といって断る。
2.「お手伝いしましょう」といって協力する。
3.「専門家を紹介します」と言う。
もちろん、顧問税理士の先生が顧問先の力になるのがベストです。
そういう意味では、3の方向性もOKでしょうね。しかしながら、
まず、大前提として、以下の点について、知ってほしいと思います
<以下の経営状態であること>
1.法人と経営者との関係の明確な区分・分離
2.財務基盤の強化
3.財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透
たとえば、1の点についてですが、これはどういう判断基準になる
「こうした整備・運用の状況について、外部専門家(公認会計士、税
つまり、「税理士さんが検証を実施して、その結果を銀行に開示し
ガイドラインには、外部専門家(会計士、税理士、弁護士など)と
経営者がガイドラインの内容を知れば、やはり、先ずは顧問税理士
そこで、「やはり、当事務所ではではお手伝いできません」となっ
また、経営者保証を外せる会社さんの場合は、やはり、それなりの
そういう顧問先が他の税理士事務所に相談しにいくことになるかも
この状況は決して好ましくないですよね・・・。
また、この逆のパターンだってあり得ます。つまり、「経営者保証
当然、その企業さんには顧問税理士さんがいらっしゃるでしょうか
もし、こうなったら・・・、何だか横取りする(される)みたいで
もちろん、ガイドラインをきっかけとして、税務顧問ではなく、「
これは、見せ方やアピールの仕方次第だと思います。
経営者保証のガイドラインに沿った経営状況にするには、それなり
ガイドライン(財務基盤の強化 )においては、「経営者個人の資産を債権保全の手段として確保し
つまり、相談をうけた時点においては、まだまだ先ほどの3つの経
それなら、税務顧問を横取りするようなことはなくなります。また
今後、こういうシーンが発生する可能性は断じてあり得ない!とは
もちろん、経営者保証が全く普及せずに、「あれはいったい何だっ
要は、税理士の先生方が、このガイドラインをどう捉えるか?だと
ただ、、、私は思うのですが、現在、民法の改正等も検討されてい
よって、中小企業を支援するあらゆる分野の専門家(税理士だけに限らず!!)は、やはり、こ
そんなことないでしょうかね?
ちょっと大袈裟でしょうか。。。
最低でも、「ガイドラインとは何なのか?」、「どういうことが書
顧問先から相談されたときに、プロフェッショナルの段階までノウ
そして、「当事務所ではこの分野のノウハウが乏しいので、この分
未だ「経営者保証に関するガイドライン」を読んだことがないとい
http://www.zenginkyo.or.jp/
3回読めば、何となくわかります。
5回読めば、全体像が把握できるはずです。
10回読めば、不明な点が明らかになると思います(苦笑)。
是非、読んでみてくださいね。
このコラムを書いた人

吉田学 氏
Manabu Yoshida
マイベストサポート代表。財務・資金調達コンサルタント。インブルームLLP所属。日本FP協会認定フィナンシャル・プランナー。神奈川大学法学部卒。
著書に「究極の資金調達マニュアル(こう書房)」「社長のための資金調達100の方法(ダイヤモンド社・共 著)」「税理士・会計事務所のための資金調達ガイド (中央経済社)」等がある。